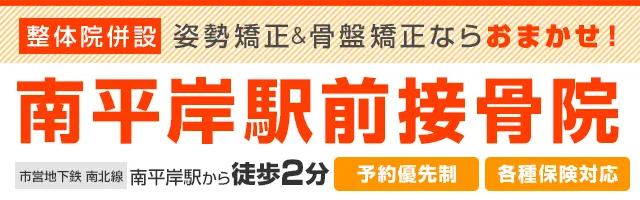肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

ランニング中、突然太ももやふくらはぎに痛みが出た
→肉離れは、急激に筋肉への負荷がかかってしまう動作に筋肉が対応できない場合に起こります。
階段昇降やジャンプをすると太ももが痛い
→ジャンプ動作は、大腿四頭筋や下腿三頭筋に負担がかかりやすく切れやすい動作になります。
重い物を投げたときに腕や背中、胸が痛くなった
→上半身での動作では、野球や陸上の遠投などでなりやすい動きになります。
運動したら、痛みとともに皮膚が青くなった
→肉離れは3つのステージに分けられており、皮下出血班が出た場合、ステージ2の可能性があります。
『ブチッ』、『バチッ』といった何かが切れた音を聞いた
→自覚症状で切れるような感覚があった場合、肉離れの可能性が高いです。
肉離れで知っておくべきこと

1)すぐに冷やす。ただし、冷やしすぎない
肉離れを起こした直後は、歩行を控え、直ちに冷やすことが大切です。水に濡らしたタオルでも良いので、すぐにアイシングを行いましょう。ただし、冷やしすぎないよう注意してください。
2)膝を軽く曲げ、足を上げる
病院に行くまでは、膝を軽く曲げ、ソファやクッションなどを使って下肢を挙上(足を高く持ち上げた姿勢)すると、痛みが軽減することが多いです。患部を心臓よりも高い位置に上げることで、肉離れによる膨張(腫れ)を防止したり、軽減が期待できます。
3)移動時は患側に体重をかけない
肉離れになってしまった場合、患側(けがをした側)に体重をかけないことが非常に重要です。移動する際は、誰かに肩を貸してもらったり、おぶってもらうなどして、負担を軽減するように心がけましょう。
症状の現れ方は?

肉離れは筋肉が部分的に断裂することによって起こるけがで、いくつかの典型的な症状があります。
1. 急激な痛み
肉離れが発生した瞬間に鋭い痛みを感じることが一般的です。
2. 腫れ
影響を受けた部位が腫れることがあります。特に、炎症が起こると腫れが目立つ場合があります。
3. 青あざ
血管が切れることで、皮膚の下に血液が溜まり、青あざができることがあります。
4. 動かしにくい
該当の筋肉を使用したり、動かしたりすることが難しくなる場合があります。
5. 筋力の低下
肉離れがあると、その筋肉を使う力が弱くなることがあります。
その他の原因は?

その他の原因として挙げられるのは、筋肉の柔軟性の低下です。
柔軟性が低下すると筋肉が硬くなってしまいます。筋肉が硬くなると、筋肉が常に収縮して縮められている状態になります。その状態から急に運動を始めてしまうと、肉離れを引き起こす可能性があります。
また、水分不足でも肉離れが起こる場合があります。水分が不足すると筋肉に必要な水分も不足し、柔軟性が失われてしまいます。それによって肉離れを引き起こす可能性があります。
そのため、ストレッチや運動前のウォーミングアップ、水分補給をしっかりと心掛けることで、肉離れの予防が期待できます。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放っておくと、持続的な痛み、運動制限、筋肉のこわばり、筋力の低下といった症状が起こる可能性があります。特に肉離れを起こした箇所を動かそうとすると、上記の症状を感じることが多いと思われます。
肉離れを起こした箇所に瘢痕組織が形成されることで、動かす際に通常通り筋肉の柔軟性が発揮されないため、運動制限やこわばり、痛みといった症状が引き起こされます。瘢痕組織は通常の筋肉や皮膚などの組織よりも厚く硬い組織でできているため、後遺症となるさまざまな症状を引き起こすことがあります。
肉離れを発症した箇所によって症状は異なりますが、当院にご来院される患者様の多くは、運動制限や筋肉のこわばりが残っていることが多いように感じます。
当院の施術方法について

肉離れの施術は、安静と固定が基本となります。
肉離れ発生後すぐの当院での施術は、アイシングと包帯やテーピングでの固定施術となります。包帯やテーピングで比較的早期に裂けた繊維を寄り添わせ、修復の手助けをする施術を行います。
急性期を過ぎた頃からは電気施術を行い、血行を良くすることにより損傷部位を再生するため、裂けてしまった患部に栄養を届ける施術を行います。そして、肉離れの患部がくっついてきた段階で、関節の動かし方や歩き方の指導を行い、早期回復を促す施術を進めていきます。
また、再度肉離れを起こさないために、完全回復後は予防として筋膜ストレッチをおすすめしています。肉離れの際に収縮した筋肉を元の長さに戻すことも再発予防につながります。
改善していく上でのポイント

肉離れを軽減していく上でのポイントは、まずRICE処置と呼ばれる応急処置を行うことです。
次に、肉離れで断裂した筋繊維を修復させるためには、必要な栄養をしっかり摂ることが重要です。筋肉の回復に必要な良質なタンパク質を摂取することが推奨されています。鶏肉・豚肉・牛肉などの肉類や魚、豆腐や納豆などの大豆製品を摂りましょう。
また、ビタミンB6も意識して摂りたい栄養素です。ビタミンB6は代謝を促す作用があり、まぐろの赤身、牛レバー、鶏ささみ、鶏むね肉、鮭、バナナなどに多く含まれています。
食事だけでタンパク質やビタミンB6が十分に摂れない場合もあります。その場合には、プロテインやサプリメントを取り入れるのもおすすめです。
肉離れを起こした場合、症状に合わせて施術が変わってくるため、整形外科や整骨院を受診することをお勧めします。
監修

南平岸駅前接骨院 院長
資格:鍼師、灸師
出身地:北海道中標津町
趣味・特技:サッカー観戦、スニーカー集め