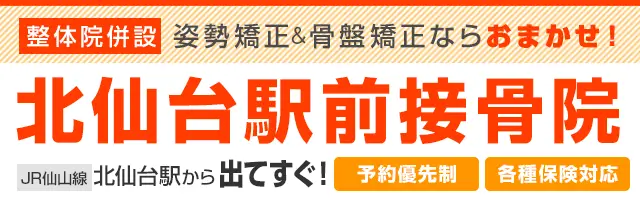オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

運動後や日常動作で膝の痛みが続いている
好きなスポーツが思うようにできない
なかなか回復せず不安を感じている
膝の形が気になるようになった
再発しないか不安を抱えている
成長期だからと放置してしまっている
オスグッドについて知っておくべきこと

1. 発症原因とメカニズム
オスグッド病は、膝の脛骨結節(膝の下の出っ張り部分)に炎症が起こるスポーツ障害です。成長期の子どもやティーンエイジャーに多く見られ、特に激しい運動やスポーツによって膝に繰り返しストレスが加わり、大腿四頭筋腱が脛骨結節部分を引っ張ることによって発症します。
2. 症状
膝の前面や脛骨結節部分に痛みが出る
走る、ジャンプ、階段の上り下りなどで痛みが悪化する
膝の腫れや膨らみが見られる場合がある
休息によって一時的に痛みが和らぐが、運動再開により再発する可能性がある
3. リスク因子
成長期(10〜16歳):骨の成長と筋肉の発達にアンバランスが生じやすい時期です。
運動習慣:バスケットボール、サッカー、陸上競技などジャンプや激しい動きが多いスポーツに取り組むお子さまに多く発症します。
4. 施術方法
休養とアイシング:痛みがある場合は運動を控え、患部を冷やして炎症を抑えます。
ストレッチと筋力強化:大腿四頭筋やふくらはぎの筋肉の柔軟性を高めることで、膝への負担の軽減が期待されます。
サポーターや膝の保護:膝の安定性を高める目的でサポーターを使用することもあります。
医療機関の評価:症状が強い場合には、整形外科での評価や物理療法が勧められることもあります。
5. 回復までの時間
オスグッド病は、成長が完了することで症状が自然に軽減されることがあります。多くの場合、14〜16歳頃に落ち着く傾向がありますが、症状の度合いや施術の状況によっては、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。
6. 予防
十分なストレッチとウォーミングアップ:スポーツ前後にストレッチを行い、筋肉の柔軟性を高めることが大切です。
筋力強化:大腿四頭筋や膝周囲の筋肉を強化することで、膝への負担の軽減が期待されます。
適切な休息:運動を継続する中でも、適度に休息をとることが予防に繋がります。
症状の現れ方は?

オスグッドの主な症状とは?
膝の痛み
- 痛みの場所:主に膝の前面、特に膝の下部にある脛骨結節(膝下の骨の出っ張り部分)に痛みが集中します。
- 発症時期:成長期のお子さまや若年層に多く、運動を始めた直後や、激しいスポーツの後に痛みが現れることがあります。
運動後の痛みの悪化
- ジャンプや走る動作:バスケットボール、サッカー、陸上競技などで膝に負担がかかると、痛みが強くなる傾向があります。特に走行やジャンプ動作時に痛みが出やすいです。
- 階段昇降:階段の上り下りでも膝に負担がかかり、痛みを感じることがあります。
膝の腫れや膨らみ
- 脛骨結節部分が腫れたり膨らんだりすることがあり、炎症が起きている状態と考えられます。触れると痛みを感じるケースが多いです。
膝の硬さやこわばり
- 痛みが強い場合、膝周辺の筋肉が緊張し、動かしづらくなることがあります。そのため、膝の可動域が制限されることもあります。
圧痛
- 脛骨結節部分を押すと痛みを感じるケースが多く、局所的な圧痛として現れます。
休息による症状の軽減
- 運動を控えて安静にすると、痛みが和らぐことが多く見られます。特に夜間や運動後に痛みが強まり、休養をとることで軽減されることが一般的です。
痛みの周期的な変動
- 初期の段階では軽い痛みで済むこともありますが、運動を繰り返すことで症状が悪化することがあります。一時的に軽減された症状が、再び強くなるケースもあります。
その他の原因は?

オスグッドの主な原因について
成長期における骨と筋肉のアンバランス
オスグッドは成長期に発症しやすい症状です。この時期は骨の成長が急速に進む一方で、筋肉や腱の発達が追いつかないことがあります。その結果、膝周囲の筋肉が膝の骨を強く引っ張るようになり、膝下にある脛骨結節にストレスが集中して炎症が起こりやすくなります。
繰り返される運動や激しいスポーツの影響
バスケットボール、サッカー、陸上競技など、ジャンプや走行が多いスポーツでは、膝に反復的な負荷がかかります。このような動作が継続されることで、膝下の腱が脛骨に引っ張られやすくなり、結果として炎症が発生することがあります。
急激な運動量の増加
普段はあまり運動をしていなかった状態から、急に激しいトレーニングを始めたり、練習量が急増したりすると、膝に過剰な負担がかかりやすくなります。特に成長期のお子さまは、骨と筋肉の発達バランスが不安定なため、急激な運動負荷が症状の原因となることがあります。
筋肉の柔軟性や筋力の不足
筋肉の柔軟性が不足していたり、筋力が弱い場合、膝関節にかかる負担が増加します。特に大腿四頭筋が硬くなっていると、膝を伸ばす動作で膝下に大きな力が加わりやすくなり、症状が引き起こされやすくなります。
骨の発達による影響
成長期の脛骨結節部分は、まだ軟骨が多く含まれており、完全に骨化していない柔らかい状態です。この部分が繰り返し引っ張られることで、炎症や痛みが起こりやすくなります。骨の成長途中という特性上、膝下への負担が蓄積しやすい傾向があります。
遺伝的な影響
オスグッドは、家族内で発症するケースが見られることから、遺伝的な要因が関与している可能性もあります。体質や骨格、筋肉のバランスなどが遺伝的に似ていることが、症状の発症に関わっていると考えられています。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッドは放置してよいものではありません
オスグッドは「成長痛だから自然に治る」と思われがちですが、骨の成長だけが原因ではありません。
実際には、筋肉の柔軟性の低下や使いすぎ(オーバーユース)など、さまざまな要因が重なって発症することが多くあります。
痛みを我慢したまま運動を続けていると、結果として長期的に運動を休まなくてはならない状況になる可能性があります。さらに症状が進行すると、最終的に外科的な処置が必要になるケースもあります。
なぜ手術が必要になることがあるかというと、無理をして運動を続けることで、筋肉が骨を繰り返し引っ張り、軟骨の一部が剥がれてしまうことがあるからです。これにより、膝下に腫れや炎症が起こり、痛みが増してしまいます。
また、剥がれてしまった骨片が大きい場合には、自然回復が難しくなり、外科的な処置を検討せざるを得なくなることがあります。
このようなリスクを避けるためにも、早い段階で適切な施術を受け、膝への負担を軽減していくことが大切です。
当院の施術方法について

当院の筋膜ストレッチについて
当院では「筋膜ストレッチ」という施術を行っております。
この筋膜ストレッチには、上半身にアプローチをかけるタイプと、下半身にアプローチをかけるタイプの2種類があります。
オスグッドの症状に対しては、下半身へのアプローチを重視したストレッチが効果が期待できます。
オスグッドは、太ももの前に位置する「大腿四頭筋」と呼ばれる筋肉が収縮し、膝のお皿の下にある脛骨の上端部(脛骨粗面)を引っ張ることで発症することが多いです。
そのため、大腿四頭筋を柔らかく保つことが、症状の軽減につながると考えられています。
実際に、オスグッドの症状を持つ方の多くは、大腿四頭筋の硬さが見られます。
この筋肉を適切にストレッチすることで、脛骨粗面にかかる引っ張りの力を弱め、痛みの軽減が期待できます。
ただし、ストレッチの際に筋肉を過度に伸ばしてしまうと、逆に筋緊張が強まったり、痛みのある部位に負担がかかってしまう可能性があります。
そのため、ストレッチのポイントとしては「軽く伸ばされている感覚」がある程度で止めることが大切です。
「痛気持ちいい」と感じるまで伸ばしてしまうと、後に筋肉がさらに硬くなってしまったり、膝への負担が増える恐れもありますので、注意が必要です。
改善していく上でのポイント

オスグッドは、ジャンプやキック、シュートなどによる大腿四頭筋の伸縮、使いすぎ、または同じ動作の繰り返しによって発症することが多いです。膝に痛みを感じ始めた場合には、しばらく運動を控えて安静に過ごすことが第一です。
ただし、部活動に励むお子さまにとっては、大切な時期に十分な練習ができないことから、スポーツの上達に影響が出るのではないかと不安になり、焦りを感じる方も少なくありません。
周囲の仲間が順調に成長していくなか、自分だけが練習に参加できず、上達のペースが落ちてしまうことで、試合への出場機会を逃してしまったという声も耳にします。
しかし、痛みがある状態でスポーツを続けても、痛みによってパフォーマンスが低下し、集中できないケースが多く見られます。そのため、焦らずに施術を優先し、症状の軽減を目指していくことが大切です。
監修

北仙台駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:山形県山形市
趣味・特技:野球観戦、サウナ