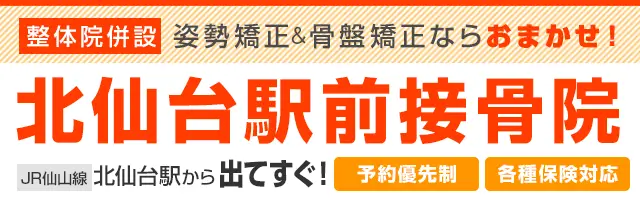肉離れ

こんなお悩みはありませんか?

肉離れの悩み例として、以下のようなものが考えられます。
日常生活に支障が出る
→肉離れを起こすと、歩行や階段の上り下りが困難になる場合があります。日常的な動作にも痛みを感じ、通勤や買い物などの活動に影響が出ることが多いです。
スポーツや運動ができなくなる
→運動中に肉離れを起こした場合、回復するまでの間、運動が制限されることが一般的です。特に競技スポーツを行っている人にとっては、トレーニングや試合に参加できないことがストレスとなります。
再発の不安
→一度肉離れを経験すると、同じ部位で再発することを心配する人が多いです。完全に治っていない状態で運動を再開すると、再度肉離れを起こすリスクが高まります。
仕事に影響が出る
→肉離れが原因で仕事に支障をきたすこともあります。特に、立ち仕事や肉体労働を必要とする職種では、長期間の休業が必要となることもあります。
回復の遅さに対する不安
→肉離れは完治までに時間がかかることがあり、その過程で痛みや不便を感じ続けることがストレスになります。また、治療法やリハビリの効果がすぐに現れない場合、治療の効果に対して不安を抱えることもあります。
こうした悩みを抱える人が多く、適切なリハビリや再発防止のための対策が重要です。
肉離れで知っておくべきこと

肉離れは、筋肉の一部が急激な負荷によって損傷する状態です。運動中や無理な動作が原因で発生し、特に太ももやふくらはぎでよく見られます。症状としては、突然の痛みや腫れ、動かしにくさなどが挙げられます。
応急処置としては、安静にし、冷やし、圧迫し、足を高くする「RICE処置」が推奨されます。「RICE処置」とは、Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)を指します。無理に動かすと状態が悪化する可能性があるため注意が必要です。
予防には、ストレッチや筋力トレーニングが効果が期待できます。また、適切な休養を取ることが重要で、無理をせず痛みが引いてから徐々にリハビリを行うことをおすすめします。筋力や柔軟性を回復させることで再発を防ぐことにつながります。
症状の現れ方は?

肉離れ(筋挫傷)は、筋肉の一部が部分的または完全に断裂した状態を指します。一般的な症状の現れ方は以下の通りです。
1. 痛み
急激な鋭い痛みが感じられることがあります。通常、運動中や急な動きがきっかけとなり、その場で動けなくなることもあります。
2. 腫れ
筋肉が断裂すると、その部分が腫れてきます。腫れは数時間から数日にかけて徐々に現れることが多いです。
3. 内出血(あざ)
重度の場合、断裂した筋肉周辺に血液が漏れ出し、皮膚に青黒いあざが現れることがあります。
4. 筋肉の弱化
断裂した筋肉を使用すると、力が入らなかったり、普段の動きが制限されることがあります。痛みの影響で、動作が難しくなることが一般的です。
5. 硬さや緊張感
筋肉が硬く感じたり、収縮したような緊張感が持続する場合があります。
肉離れが発生した際は、早期に適切な処置を行うことが重要です。医師の診断を受け、治療やリハビリを適切に進めることで、回復が期待できます。
その他の原因は?

肉離れの主な原因は、筋肉に過度な負荷やストレスがかかることによって発生します。具体的な原因は以下の通りです。
1. 急激な動き
スポーツや日常生活での急なダッシュ、ジャンプ、急停止など、急激な動作によって筋肉が大きく伸びたり縮んだりすると、筋肉が対応しきれず断裂することがあります。
2. 筋肉の疲労
長時間の運動や繰り返し同じ筋肉を使うことで筋肉が疲労し、柔軟性や反応が低下します。この状態で無理に動くと、筋肉が損傷しやすくなります。
3. 準備運動不足
スポーツや運動を始める前に適切なウォーミングアップを行わないと筋肉が硬くなり、突然の動きに対応できず肉離れを起こす可能性があります。
4. 筋肉の柔軟性不足
筋肉が硬い状態では、伸び縮みする範囲が限られてしまいます。このような状態で無理に動かすと、筋肉が断裂しやすくなります。
5. 寒冷環境
寒い環境では筋肉が収縮しやすく、柔軟性が低下します。この状態で激しい運動を行うと、肉離れのリスクが高まります。
6. 過去のけが
過去に肉離れや他の筋肉のけがをしたことがある場合、その部位は再発しやすいとされています。
これらの原因を予防するためには、日頃から筋力トレーニングやストレッチを行い、運動前のウォーミングアップを適切に実施することが大切です。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れを放置すると、以下のような悪影響が生じる可能性があります。
1. 回復の遅れ
適切な施術を行わない場合、筋肉の回復が遅れ、完全に治癒するまでの期間が長引くことがあります。特に重度の肉離れでは、放置することで筋肉がうまく再生されず、機能が低下することが懸念されます。
2. 慢性的な痛みや不快感
肉離れを放置することで、痛みが長期間続き、慢性的な痛みや違和感が生じる可能性があります。この痛みは動作時に悪化し、日常生活やスポーツ活動に支障をきたす場合があります。
3. 筋肉の柔軟性や力の低下
断裂した筋肉が正しく治癒しない場合、筋肉の柔軟性や力が低下し、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。また、筋肉のバランスが崩れることで、他の筋肉や関節にも負担がかかる場合があります。
4. 再発のリスク増加
施術を受けずに回復が不十分なまま運動を再開すると、再び肉離れを起こすリスクが高くなります。一度傷ついた筋肉は再発しやすく、同じ部位で繰り返し損傷を受ける可能性があります。
5. 他の部位への影響
肉離れを起こした筋肉をかばうことで、他の筋肉や関節に負担がかかり、別の部位で新たなけがや障害が発生するリスクも高まる場合があります。
早期に適切な治療とリハビリを行うことで、肉離れの悪化を防ぎ、回復を促進することが重要です。
当院の施術方法について

当院での肉離れの施術は、主に痛みの軽減や回復を促進するためのアプローチが取られます。具体的な施術方法は次の通りです。
1. 電気施術
低周波や超音波を使用し、筋肉の緊張を和らげて血流を促進し、痛みの軽減が期待できます。
2. マッサージ
損傷部位周辺の筋肉をやさしくほぐすことで、血行を促進し、回復をサポートします。
3. テーピングや包帯
関節や筋肉を保護し安定化させるために、テーピングを施すことがあります。
4. ストレッチ・リハビリ
適切なストレッチや運動療法を行うことで、筋力回復や再発予防を目指します。
施術は個々の状態に合わせて行われ、無理なく回復を促します。
改善していく上でのポイント

肉離れを改善するためのポイントは、適切な休養とリハビリを組み合わせた段階的な回復が重要です。具体的には、以下の点がポイントです。
1. 安静を保つ
最初は損傷部位を動かさず、安静にすることで回復を促します。無理な動きは症状を悪化させる可能性があります。
2. 適切なアイシングと圧迫
腫れを抑えるために、最初の48時間は冷やしながら圧迫を行います。
3. 徐々に運動を再開する
痛みが軽減したら、医師や整骨院の指導のもとでストレッチや軽いリハビリを開始し、筋力を徐々に取り戻します。
4. 再発予防
完全回復後も、筋力トレーニングや柔軟性を向上させる運動を継続することで、再発を防ぐことが期待できます。
これらを守ることで、安全かつ確実な回復を目指すことができます。
監修

北仙台駅前接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:山形県山形市
趣味・特技:野球観戦、サウナ